「上司になりたてで、どのようにチームを作っていけばいいのか分からない。。」
「部下が育ってくれない。。」
ちょうど3年前、上司1年生になりたてのわたしがそうでした。
わたしは20代から30代前半まで「プレイヤー」として生きてきました。
 ヨシタカ
ヨシタカ上司に恵まれ、先輩や後輩にも助けられながらなんとか『成果』をだしてきました。
それが幸いにも認められ『チームリーダー』になったんです。
世間で言われるところの『係長』です。
前回、30代の悩みとしてこんな記事を書きました。
30代はちょうど『係長』を任せられる年代。
とはいえ『係長』は課長と違って管理職ではありません。
自分で責任のある仕事をしながら部下の仕事の教育や指揮をとる、いわゆるプレイングマネージャーです。
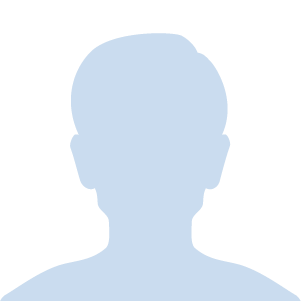
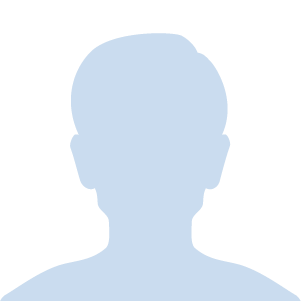
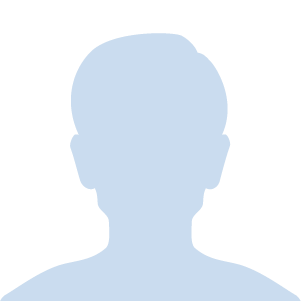



えっ、まぢっ!?
これまで『プレイヤー』としては優秀だったかもしれない。ただ、責任を持って人を育てるとなると、こりゃ大変。
それから『上司』としてのわたしの試行錯誤が始まりました。
自分の頭で考えて行動する部下の育て方の3つのコツがこちら。
- 部下に指示しない
- 部下に答えを教えない
- 部下のモチベーションを上げようとしない
今回は「自分の頭で考えて動く部下の育て方 上司1年生の教科書」について、わたしのこれまでの『上司』としての部下育成のトライ&エラーも含め、ご紹介します!
部下がいない方は『後輩』として読みかえていただければと思います。
『上司』としての部下育成とは?
今まで『先輩』として後輩の指導はしたことがあるけど、『上司』としてのチームづくりや部下育成は初めて。
チームメンバーは年下だけでなく、同年代や年上だったり。
当時のわたしはこう思いました。



やばい!部下育成とか出来るのかな。。
個人としての成果を出すことには若干の自信がありましたが、チームの成果が求められるとなると話は別です。
チームリーダーの役割を一言でいうと、「チームを引っぱり、チームとして業務を完遂し成果を出す」こと。
ざっと書き出すだけで色々とあります。
- ゴール(目標)の共有
- 部下への指導・育成
- 適材適所の仕事の割り振り
- チームの業務進捗管理
- 他部署との連携
などなど。
30代になると、自分のことばっかりやるなよ!そろそろ周りのことや会社のことも考えろよ!というお年頃なわけです。
この中で最も期待されていることが部下の指導・育成。
今までは部下育成に責任はありませんでしたが、チームリーダーはそこに責任がともなう。
言い換えると、「部下が自分の力で業務をやり遂げる状態にする」ことがチームリーダーの仕事の1つです。



『上司』になるってなかなか大変です。。
部下に指示するべからず
まずは、わたしの失敗談をご紹介。



指示がいちいち細かい!
これ、わたしがチームリーダーになりたての頃にやってしまった失敗です。
今もたまに細かいかもしれません(部下に指摘されて気付きます。)
そもそも指示とは・・・
物事をそれと指し示すこと。指でさすこと。指図すること。命令。
たとえば、「今週中に3社から見積もりを集めて下さい」などですね。
チームリーダーになりたての頃、まず課長に言われました。
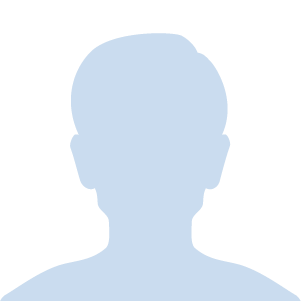
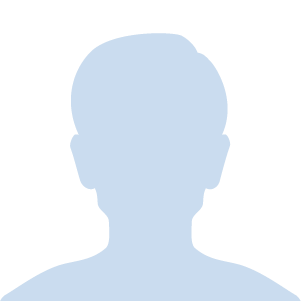
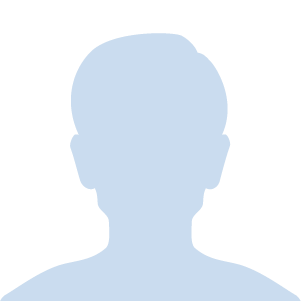



はい!?ToDo(トゥードゥー)ですか?
ToDo(リスト)とは、日常業務で「行うべきこと」を記録しておくこと。 たとえば「○月○日までにやらなければいけない仕事」など、仕事内容に期日を組み合わせて登録することで管理します。 また、カテゴリに分類し、重要度により管理をします。
前任の方から引き継いだものの、まずは各業務の状況の把握から開始。
そこからざっとやるべきことを並べ、部下に指示(依頼)します。



これをいつまでにお願いします。この時はこれに注意して下さい。あ、これも気をつけて。他にも、あれとこれと・・・
↑これ、一番やってはいけない例です。
部下に依頼する以前の問題。
これでは、上司失格です。



背景や目的の共有も出来ていませんでした。。
なぜそれをする必要があるのかをまずは共有する。
もしかしたら、部下に手取り足取り、
「次はこうするんだよ」
と指示をどんどん出したほうが仕事が早く進むと考えてしまう方もいるかもしれません。
しかし、部下自身が考えることをする機会(チャンス)を奪ってしまい、結果として『指示待ち人間』になる原因となってしまうんです。
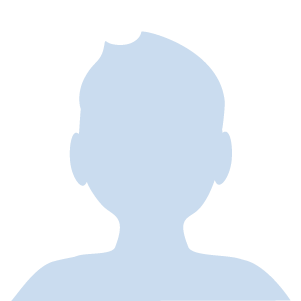
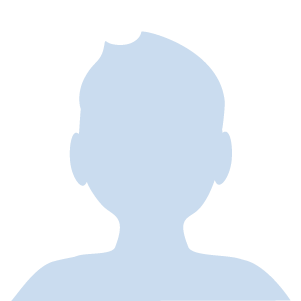
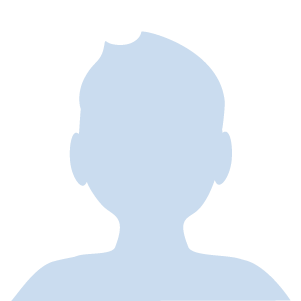
となるわけです。
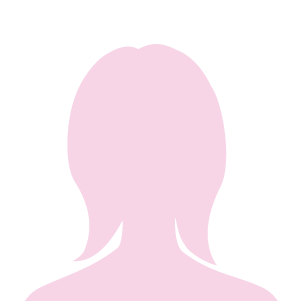
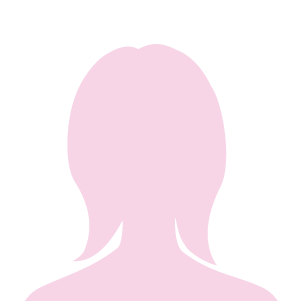
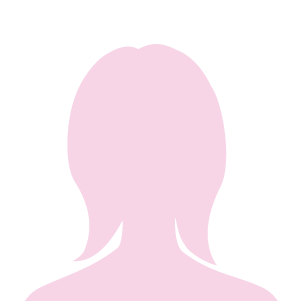
どうせわたしは作業員なんでしょ。なら言われたことだけやろうっと。
ってね。
これでは部下は育ちません。
「やらされている感」のある仕事ってつらいです。。
いわゆる「雑用」にだって工夫の余地があるかもしれませんし、そもそもの目的を伝えればもっといい方法を思いつくかもしれません。
ただ「作業」を依頼するだけでは部下は育ちません。
「考える」機会を与える必要があります。
まずは部下に依頼する場合は、その背景や目的を伝え、どうすればいいか部下自身に考えてもらうことが大切です。
そんな時は部下に聞くんです。



どうすればいいと思います?
ただし、これをやり過ぎると逆にストレスを与えすぎてしまうので要注意。
- 一気に教えすぎない
- 自分でやってしまいすぎない
- 教えなさすぎない
部下に答えを教えるべからず
もしかしたら部下育成なんて出来ないと不安を感じている方もいらっしゃるかもしれません。
口下手だし、威厳もないし、指導力もないし、教え方も下手だし・・・。
いいんです。口下手でも、威厳なんてなくても。
上司の仕事は、部下の意欲を引き出すことです。



でもどうやって?
さきほどの例でもありましたが、「指示が細かい」と部下は熱意を失います。
部下が熱意を持ち、注意力を高め、初歩的なミスがどんどん減っていくように指導するには、
「何を教えないか」が大切です。
人間は丁寧に教えてくれる人がそばにいると考えなくなります。
基本的に人間はラクをしようとする生き物です。
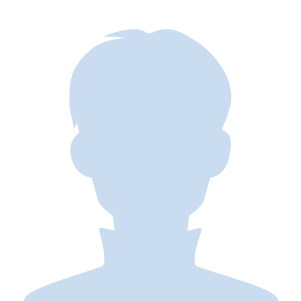
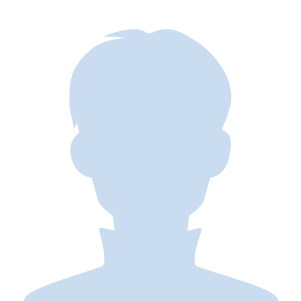
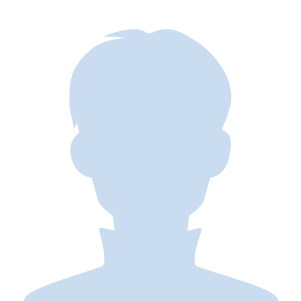
となるわけです。
ここで必要となるのが、「自己効力感」。
自分でもなんとか成し遂げた!
という感覚です。
何事かを自分の力で成し遂げたとき、そんな「自己効力感」が感じられたとき、人は自信を持ちます。
そして、もっといろいろなことにチャレンジしようという熱意が湧く。
ところが先回りして教えてしまうと、この自己効力感を感じる機会を失ってしまう。
「それだと失敗するよ。こうした方がいいよ」
先回りして解決策や答えを教えてしまうと、自分自身の力で答えを見つけ出すという快感を味わえず終わってしまう。
すると、仕事がつまらなくなり、指示待ち人間になる。
「できない」が「できる」に変わる瞬間をいかに部下に味わってもらうか。
そこが上司の腕の見せ所です。
部下に気持ちよく働いてもらう。
受動的ではなく、能動的に。



まぁ現場ではそんな余裕ないよ!というのも実情なんですけどね。
ということで、まずはお手本を見せるのも大事です。
- 上司がお手本を見せる
- 部下に頭の中で反芻する時間を与える
- 実際にやってもらう
- きちんと褒めつつ、今後の工夫を促す
部下のモチベーションをあげようとするべからず
じゃあ、部下のモチベーションを上げればいいんでしょ!
という考えになりますよね。
「答えを教える」よりも「できるようになった快感」を味わってもらう。



でもどうやって?
またここでもわたしの失敗談です。
成功体験を積ませてあげればいい!ということで、結局手伝いすぎてしまったんです。
するとまた『自分の頭で考えない人材』の出来上がりです。
上司になりたてのわたしはなんでもアドバイス。
「ああすればうまくいくよ。こういう場合はこうすればいいよ。」
まさに『転ばぬ先の杖』状態。
上司が熱心に指導したつもりでも、部下にとっては創意工夫する機会を失っているわけです。
そして「やらされてる感」が強まる。
つまり、部下のモチベーションを上げようと上司が働きかけると、部下のテンションはだだ下がり。
部下の意欲をかき立てるには、よけいなことをするよりもよけいなことを減らすほうがよっぽど良い。
もっと言うと、モチベーションを直接上げようとするのではなく、モチベーションが下がってしまう要因を除去するように努力するべし。
そうすれば意欲なんてものは勝手に湧いてくる。
上司の仕事は、部下に働いてもらうこと。
働いてもらうには、働くこと自体を楽しみ、意欲をもって取り組んでもらうこと。



でもどうやって?
部下が「できない」ことが何か?部下の成長の段階に合わせて「できない」を提供する。
ここまで基礎技術を習得したら、きっと部下は次の「できない」を「できる」に変えられるだろうと、見通しを立てた課題を与えるのも上司の腕の見せどころ。



子育てにも通ずるものがありますね。
できるようになったことを驚き、一緒になって喜ぶ。



わぁ、できるようになったね!やったじゃん!!どうやったの?!
工夫を面白がり、そしてまた成長を見守る。
どんなことを考え、どういう風に挑戦したのか。
成長するためには、とても大切な経験です。
- 基礎能力を積み上げる
- 次のステップへの見込みが立ったらちょっと背伸びさせてみる
- 一度お手本として上司がやってみせる
- 見守りながら一度部下にやらせてみる。口出ししない。
- いつでも上司に相談できる状態を用意しておく
上司1年生がこころがけるべきこと
今回は、わたしのこれまでの経験も含め、上司1年生がこころがけるべきこと、部下指導のコツをご紹介しました。
- 部下に指示しない
- 部下に答えを教えない
- 部下のモチベーションを上げようとしない
なんでもかんでも手取り足取り懇切丁寧に『指示』すると、『自分の頭で考えない指示待ち人間』になってしまいます。
なので、部下には指示せずに、そして成果を求めずに、「工夫」を求めるようにしましょう。



どんな工夫したの?
「できない」が「できる」に変わる瞬間を何度も味わってもらう。
結果をほめず、工夫を尋ね、工夫を面白がる。
この方法は新人だけでなく、「ベテラン」の方にも有効です。
どんどん能動的になっていく様子を喜びながら、楽しく試行錯誤してみてください♪
よりよりチームづくり、部下育成が出来ますように。
自分の頭で考えて動く部下の育て方 上司1年生の教科書、おすすめです。



なかなか良書でした♪
ぜひ部下育成にお悩みの上司の方はご一読あれ。
30代の悩めるあなたへ、こちらの記事もぜひご覧ください。
関連記事出世と仕事。30代の悩める君へ。上に行く人に求められるスキル・考え方とは?
関連記事思考の整理学を読んだ感想、あなたはグライダー人間?飛行機人間?
女の子の育て方の記事もオススメです。





コメント